
こんにちは
スキーインストラクターのニセ外人です
さていきなりですが、時代と共に用具も変わり、それに伴い技術も変化してきました
棒状のスキー時代は、外向傾という形(かたち)にこだわり、ズレや止めるような滑りが流行った時もありました
時は流れ現在はカービングスキーとなり、おのずとその板の特性を生かした滑りが主流となってきてます
今回は級別テスト、プライズテストに関連させてそのお話しをします
それでは本日も開店です
カービングの意識
イントラの仕事の一つとして「バッジテスト」があります

級別・プライズの検定や事前講習等のことね

毎年たくさんの方を指導させて頂いてます
そんな中、時代と共に「上手さの基準・合格の基準」が変わってきたのも事実です
先にも書いた「棒状のスキーとカービングスキー」では滑り方をはじめ色んな面で違います
また近年は、よりカービングスキーの特性を生かした滑り方が高い評価を得てる・・・・そんな風潮も目立ってます
2級バッジテスト
先日、2級を受験される方を対象とした講習の講師を担当させて頂きました
2級というとある程度スピードも抑え気味で、安全にコントロールできれば合格基準に達すると思いますが・・・・

先日行った講習にはアルペンをやったことのある若い女の子が入ってたんだ
その子の滑りはオープンスタンスで常にカービング
スピードも速く、正にアルペンっぽい
2級の種目には基礎パラターンという「基礎」って文字が含まれてますが・・・・もちろん高い技術の人が、わざわざズレや止める滑りをする必要はありません
レッスンではその滑りを修正することなく、それを生かして種目をこなしたんだよね
後日、2級を受験して、とてつもないプラスで合格してました
1級でも同じ
1級の小回りも「基礎」という言葉が付いていて正確には「基礎パラレルターン小回り」なんて種目になってます
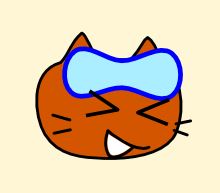
しかーし、基礎にこだわる必要はありません
「基礎」という曖昧な言葉尻にとらわれず、質の高いものに関して敢えて質を落とさせる必要もないと思うところです
テククラの滑り
過去の記事でも書いてるように、最近のテククラで合格される方の滑りは如実にカービング性能を生かした滑りになってる事は間違いないです

大回りも、もちろん小回りも
全てフルカービングってわけではないですが・・・・
カービング要素は多く、ズレるとしてもカービングの板の傾きの中でズレがコントロールできるのが理想と思ってます
また、小回りって斜度がキツくなると大回りと全くかけ離れた「The 小回り」(振ったり止めたりする)になりがちですが、こういった場面でもカービングチックにした方が良さそうです

具体的には大回り要素を残した、パッと見アルペンチックな操作が評価されてるように感じます
まとめ
現在、基礎スキーのバッジテストに挑戦される方のほとんどがカービングスキーを履いてます
その中で、板の特性を生かした滑りというのがカービング(レールターン)です
ただ、カービングと言っても、これこそが奥が深いと思うのです
圧を掛ける、深く回す、内脚使う、内脚畳む、切り替えはどうする?腰の向きは?
攻略するカギはカービング(レールターン)を追求する・・・・
なーんて思うところです
本日はカービングについて記事にしました
「あ、いつもよりカービング意識して小回りしてみよ」なーんて思った方はぽち凸してね
↓ ↓


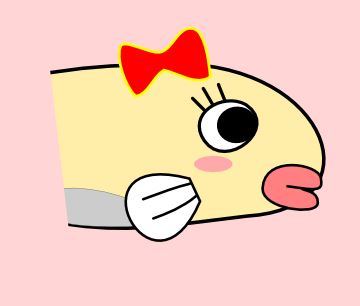



コメント